平成26年度第1回「2020.30」推進懇話会
常任理事・医療関連事業部長 藤井 美穂
 日本医師会では、平成22年12月に閣議決定された内閣府の「第三次男女共同参画基本計画」の中で、社会のあらゆる分野の女性が占める割合において、2020年までに指導的地位に少なくとも30%程度とする目標の達成が課題とされたことを受け、日本医師会においても、積極的改善措置(ポジティブ・アクション)を進めております。日本医師会の活動への理解を深めていただくことはもちろん、今後の活動への参加を期待し、当懇話会を開催しております。
日本医師会では、平成22年12月に閣議決定された内閣府の「第三次男女共同参画基本計画」の中で、社会のあらゆる分野の女性が占める割合において、2020年までに指導的地位に少なくとも30%程度とする目標の達成が課題とされたことを受け、日本医師会においても、積極的改善措置(ポジティブ・アクション)を進めております。日本医師会の活動への理解を深めていただくことはもちろん、今後の活動への参加を期待し、当懇話会を開催しております。 今年度の第1回目の懇話会が10月4日(土)に日本医師会館で開催され、日本医師会の組織と医師賠償責任保険制度、年金制度、日本医学会、女性医師支援センターなどの事業内容と、日本医師会雑誌の発行、理事会・常任理事会における意思決定プロセス、各委員会や協議会、ブロック医師会連合総会などの日本医師会の運営について説明がありました。
質疑応答では、男性は女性に参画してほしいと言うが、時間外に働くことや家事への意識改革をしない限り難しいのではないか。幼児期の保育支援は進んできているが、小学校就学時以降の支援を充実させるよう、日本医師会で意見を吸い上げてほしい。教育研修プログラムの中で、子育て中の医師の経験やどんなサポートがあれば研修を続けられるのかアドバイスがほしい。などたくさんの意見が出されました。
北海道医師会からは、会員の札幌いしやま病院の川村麻衣子医師と札幌徳洲会病院救急総合診療科プライマリ科中川麗医師、札幌医科大学脳神経外科大坂美鈴医師の3名に出席していただきました。
当日参加された先生から感想記をお寄せいただいたので、以下に掲載します。
札幌いしやま病院
川村 麻衣子
ある日北海道医師会から『2020.30』推進懇話会の参加者募集についてという案内が届いた。医師会から懇話会の案内が届いたのは初めてだった。日本医師会、内閣府の閣議決定、懇話会開催など難しい言葉が並び、私には関係ない、なぜこんな案内が届いたのだろう?と、一度は目を通したものの、その案内状はそのまま裏面コピー用紙置き場へと運ばれた。
テレビで女性の社会進出についての話題があった際、ふとこの案内が届いたことを思い出し、夫に話したところ、日本医師会館に行くチャンスはなかなかないし、旅費も出してもらえるなら行ってみたら?ということになった。
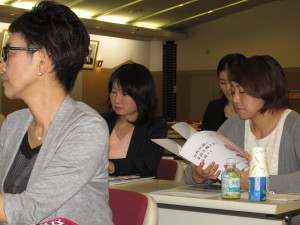 現在の勤務先である札幌いしやま病院に勤めてから札幌市医師会、北海道医師会に入会し集まりに参加したことはあったが、日本医師会の催しに参加したことはなかったし、日本医師会がどのような所なのか興味もなかった。もちろん日本医師会の会員でもない。こんな私が日本医師会館に出向くチャンスは確かにこれから先ないだろう。という気楽な気持ちで懇話会に参加することにした。
現在の勤務先である札幌いしやま病院に勤めてから札幌市医師会、北海道医師会に入会し集まりに参加したことはあったが、日本医師会の催しに参加したことはなかったし、日本医師会がどのような所なのか興味もなかった。もちろん日本医師会の会員でもない。こんな私が日本医師会館に出向くチャンスは確かにこれから先ないだろう。という気楽な気持ちで懇話会に参加することにした。 予想以上に日本医師会館は立派な建物であったし、小講堂に飾られていた歴代の会長の写真には圧倒された。みなが目指すは日本医師会会長か国会議員の道なのだろうか…と考えながら、懇話会に出席された先生の名簿を見ると、理事、院長、部長、助教など錚々たる地位にある方たちが全国から参加されていて、私のような役職もついていない平社員がくる場所ではなかったことに気付く。
それだけでも肩身が狭かったが、質疑応答での真面目な発言を聞くたびに、気楽な気持ちで参加した自分がさらに恥ずかしくなった。
しかし、日本医師会がどのような仕組で何をしているところか学習することができたのは非常に大きな収穫であったと思う。具体的にこれから何をすればいいのかは正直わからないが、今回は「日本医師会を知ろう!」という目的であったので、よしとしよう。2時間のために札幌‐東京の日帰りはきついなぁと感じた出張であった。
札幌医科大学脳神経外科
大坂 美鈴
この懇話会は日本医師会において、医師会の活動への理解を深め、各種委員会等の委員に女性会員の起用を進めるという趣旨で行われました。
日本医師会の組織と事業内容、日本医師会の運営、「2020.30」推進懇話会について説明がありました。説明はとてもわかりやすく、その後の質疑応答では時間が足りないほどでした。都道府県医師会もしくは郡市区等医師会の理事などの要職の経験者や子育てを頑張りながら働いている先生のお話も聞くことができて、とても参考になりました。
女性医師が、日本医師会内委員会の委員として活動したり、子育てをしながら医師として活躍するためにはどうしたら良いのかといった問題に取り組むには、現在活躍されている女性医師がもっと多く参加し、意見交換する場が必要と感じました。
年々、医学部学生の女性の占める割合が多くなっているのは喜ばしいことですが、妊娠、出産、育児を経験した女性医師が医師として働くことがなくなってしまうのは残念です。年々医師不足が深刻化していることを考えると子育てをしながら少しでも活躍してほしいと思いますが、難しいのが現状です。
職場に復帰するには、女性医師の環境整備だけでなく、上司、職場の理解、人員配置、夫の理解などのさまざまな問題があり、実際どういう制度があれば女性が医師を続けられるか、職場復帰できるのか、育児と仕事をしながら、どのようにスキルを維持してきたのかなど女性医師の体験等踏まえ、体制を整えていく必要があると考えます。
今後、医学教育や初期研修中にも医師会に参加する機会をもっと多く設け、日本医師会へ参加される女性が増えることを期待したいです。
今まで医師会活動にほとんど参加したことがありませんでしたので、今回、推薦して頂いた北海道医師会の関係者の皆様に深く御礼を申し上げます。
札幌徳洲会病院
救急総合診療科プライマリ科 中川 麗
福島で生まれ、東海大学を卒業、北海道へ対する漠然とした憧れもあり、就職と同時に移住いたしました。手稲区支部の先生方に、医師としてのいろはを教えていただき、この数年は厚別区支部にてお世話になっております。多忙を言い訳に、ご挨拶が遅れております先生方も多い中、このように懇話会に参加、勉強させていただき恐縮しております。
目の前の仕事にあたふたと、結婚や家庭とは縁遠い生活をしております。しかし、戦争もバブルも老いも、ずっとともに味わってきた伴侶に手を握られて眠りにつかれる方を見送る時、ふと、不謹慎にもうらやましく思うことがあるのも事実です。古稀を祝い、一回り小さくなった両親が、すれ違う乳母車を、目を細めて覗き込む姿をみると、少しせつない気持ちにもなります。
ただ、そういった心のゆらぎは一瞬で、普段は毎日に必死で、将来や家族についてじっくり考えることもなく、過ぎ去ってきました。そもそも、私には仕事と家庭を両立させるだけの器用さはなく、度量も勇気も持ち合わせていなかった。ですから、今に納得しております。幸いにも、私らしいと苦笑いしながらも、現状を受け入れ、成長を見守ってくれる方々にも恵まれました。
この数年、気づけば10歳以上はなれた研修医や学生との仕事をいただく機会が増えてきました。臨床に驚き、戸惑い、恐る恐る足を踏み入れる彼らと過ごす中、私自身がこの世界に導き入れてもらった頃を思い出します。必死の彼らと過ごしながら、次世代には、仕事だけではなく、家庭も持たせてあげたいと思うようになりました。
この会にて、多くのそれら両立に成功した先輩方のお話しを伺えて、大変勉強になりました。女性に限らず、男性も、医師としての成長と新しい家庭を築くためには、性別を超えた理解と、周囲の協力が避けがたいかと存じます。その一助となれればと思いました。
私自身が大切に育てていただいたように、いただいたものを次世代に引き継ぐことができますように。北海道の医療の発展とそこに関わるスタッフのより豊かな人生がもたらされますように。
今後ともご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

