平成26年度女性医師支援事業連絡協議会
 平成26年度の標記連絡協議会は平成27年2月27日(金)に日本医師会で開催され、最初に「国における女性医師支援の取組」と題して、厚生労働省大臣官房審議官の福島靖正氏の講演の後、6ブロックで開催された女性医師支援センター事業ブロック別会議で報告された特徴的・先進的な取り組みが紹介された。
平成26年度の標記連絡協議会は平成27年2月27日(金)に日本医師会で開催され、最初に「国における女性医師支援の取組」と題して、厚生労働省大臣官房審議官の福島靖正氏の講演の後、6ブロックで開催された女性医師支援センター事業ブロック別会議で報告された特徴的・先進的な取り組みが紹介された。北海道医師会からは、小職と女性医師等支援相談窓口コーディネーターの足立柳理先生が出席した。その他、函館市医師会依田弥奈子先生、旭川市医師会長谷部千登美先生、旭川医科大学二輪草センターの赤坂和美先生も北海道から出席した。
1.講演
国における女性医師支援の取組み
厚生労働大臣官房審議官(医政担当)福島靖正先生
全医師数に占める女性医師の割合は増加傾向にあり、医学部入学者に占める割合は約30%である。
厚生労働省では、復職支援と勤務環境改善、育児支援を支援策の柱として、女性医師バンク事業の実施、医療機関の勤務環境改善に関する指針の策定、補助対象となる保育所の保育児童数などの要件緩和を実施している。都道府県に対しては、基金による新たな財政支援制度により財政支援として、来年度も904億円の予算を確保した。
また、女性医師のキャリア支援の一層の充実に向け、地域の医療機関に普及可能な効果的支援策モデルの構築に向けた必要経費を補助する「女性医師キャリア支援モデル普及推進事業」を開始する予定である。
 日本再興戦略改訂2014を基に、女性医師による懇談会が設置され、女性医師がライフステージに応じて活躍し、働き続けやすい環境を整備するため、現場の課題や取組みの工夫のあり方などを検討し、その結果を事例集として取りまとめ、平成27年1月23日に報告書を公表した。今後は、医療機関や都道府県、関係団体を通じて広く周知し、都道府県における相談窓口や医療勤務環境改善支援センター、地域医療支援センターにおいても活用していただく予定である。報告書では、ライフイベントを抱える女性医師のニーズに応じるとともに、医療の質を確保し、患者に必要な医療を安全かつ継続的に提供していくためにも、女性医師が働き続けやすい環境整備が重要である。女性医師が自らの希望するキャリア形成を図りながら、医師としての社会的役割を果たしていく視点が必要で、性別や職種を問わず、医療従事者全体の勤務環境の整備と調和が医療の質の確保と安全かつ継続的な医療提供体制を構築する包括的な支援が必要である、とまとめられている。
日本再興戦略改訂2014を基に、女性医師による懇談会が設置され、女性医師がライフステージに応じて活躍し、働き続けやすい環境を整備するため、現場の課題や取組みの工夫のあり方などを検討し、その結果を事例集として取りまとめ、平成27年1月23日に報告書を公表した。今後は、医療機関や都道府県、関係団体を通じて広く周知し、都道府県における相談窓口や医療勤務環境改善支援センター、地域医療支援センターにおいても活用していただく予定である。報告書では、ライフイベントを抱える女性医師のニーズに応じるとともに、医療の質を確保し、患者に必要な医療を安全かつ継続的に提供していくためにも、女性医師が働き続けやすい環境整備が重要である。女性医師が自らの希望するキャリア形成を図りながら、医師としての社会的役割を果たしていく視点が必要で、性別や職種を問わず、医療従事者全体の勤務環境の整備と調和が医療の質の確保と安全かつ継続的な医療提供体制を構築する包括的な支援が必要である、とまとめられている。
2.ブロック別会議開催報告
1)九州ブロック
佐賀大学医学部社会医学講座講師 原 めぐみ先生
佐賀県で開催された「女性医師支援センター事業九州ブロック会議」で発表された、各県の特徴的・先進的な取り組みの報告と、平成26年10月に佐賀県医師会で実施した「医療機関開設者・管理者に対するアンケート」の結果の紹介があり、出産育児を支援する制度の導入はある程度充実してきたが、妊娠期・短時間勤務・代替要員の制度は不十分である。また、30・40歳代の男性の労働負担が大きく、医療界全体での勤務環境改善が必要である。今後は、女性医師のキャリア・プロフェッショナリズムの形成が課題であり、学生から生涯にわたる教育・啓発が必要と考えていると報告された。
2)中国四国ブロック
岡山県医師会理事 神崎寛子先生
中国四国9県の産休・育休中の代替医師確保の状況に関するアンケート調査の結果の紹介があった。
9県中6県が代替医師の必要性が問題となっていると回答があり、その主な理由として、大学医局へ派遣依頼をしても診療科によっては医師不足のため調整がつかない、非常勤の派遣では当直等の業務で同僚医師の負担が大きくなるなどが挙げられた。問題となっていないと回答した県では、産休・育休をとる女性医師がいない、女性医師は当直をしない外来のみの状況のため休んでも影響がないなどの理由が挙げられていたと報告された。
3)近畿ブロック
奈良県医師会勤務医部会理事・奈良県立医科大学
女性研究者支援センター 講師 須崎康恵先生
奈良県医師会の男女共同参画と女性医師のエンパワーメントをめざし、意識改革に重点を置いて女性医師の就労継続やキャリア向上に関する意識を高め、男性医師の男女共同参画の理解を深める医学教育の構築を図っており、奈良県立医科大学女性研究者支援センターと共催で平成24年度から「男女共同参画の視点に基づいた専門職としてのキャリア教育」に関する講義を医学生対象に実施している取組みの紹介があった。また、奈良県立医科大学における過去5年間の博士学位取得者のうち、女性の割合は13.3%と非常に少なく、指導的な役割を果たす女性が増えて、女性が抱える問題やニーズを強く主張できるようになれば、状況は改善されるに違いないと考えていると報告された。
4)中部ブロック
福井県医師会女性医師対策委員会
委員長 里見 裕之先生
ふくい女性医師支援センターで平成26年2月に福井県内の病院を対象に実施した、女性医師の就労支援に関するアンケート調査の結果を踏まえて行った病院訪問・女性医師との面会の訪問活動の紹介と、自身が勤務している福井県済生会病院女性医師復職支援制度について、産婦人科常勤医が減員してしまった際に、産婦人科から女性診療へのパラダイムシフトや復職したママドクター働き方が後輩女性医師の参考になり、後期研修を行う若手医師が増えているなど実際の診療現場での状況の報告があった。
ママドクターは、仕事も子育ても全て完璧にこなしたいと思っており、妥協はしたくないという強い意志を持っている。上司は自分の子育て経験を活かし、上司という立場ではなく親の目線で女性医師を支援してもらい、女性医師と上司、それぞれが持っているこだわりをお互いに尊重し、相互理解を深めてほしいとされた。
5)関東甲信越・東京ブロック
埼玉県医師会常任理事 利根川 洋二先生
埼玉県女性医師支援センターの実績と県内の病院に勤務する女性医師を対象に行った勤務環境に関するアンケート調査結果の内容について報告があった。調査結果より、医師同士の夫婦の場合は、夫の協力なしに子育ては成り立たず、女性医師が勤務を継続するためには、院内保育所・宿日免除・短時間勤務などの制度整備が必要不可欠であるとした。
また、埼玉県総合医局機構では、女性医師の復職につながればと考え、病院の現場で指導を行うことができるベテラン医師を指導医として病院に紹介する「ベテラン指導医紹介事業」の説明があった。
6)北海道・東北ブロック
北海道医師会女性医師等支援相談窓口
コーディネーター 足立 柳理先生
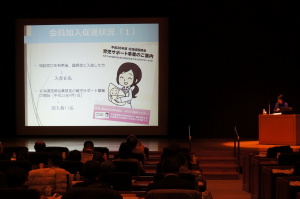 開設から3年半が経過した相談窓口事業の専用ホームページへのアクセス件数、相談件数、育児サポート事業の事前登録件数など全て順調に伸びていることと事業の取組みについて報告があった。
開設から3年半が経過した相談窓口事業の専用ホームページへのアクセス件数、相談件数、育児サポート事業の事前登録件数など全て順調に伸びていることと事業の取組みについて報告があった。また、子育て中の医師から要望の多い、製薬会社が行う研修会等への託児室併設に関して、医師を対象に開催する全ての研修会・学術講演会等において託児室を併設することと、そのための支援を医師会が行う新しい支援事業の検討を現在、製薬会社と進めていること、医師会の会員数は減少傾向にあり、女性医師支援と併せて医師会加入の促進活動も展開していることの取組みの紹介があった。
そらに、復職研修は実践に近い形で復職する医師自らが実技をする方法が一番良く、地方病院に指導医と出かけて診療をする方法は、研修中の医師にとっても貴重な時間となると同時に、地域医療にも貢献できると考え、「女性医師等復職研修・地域医療支援事業」を提案しており、研修受け入れ医療機関と地方での研修も可能な医師を確保することから始めていると報告された。
最後に質疑応答と総合討論があり、山本日医理事から、女性医師問題または男性医師についても「自助・互助・共助・公助」の四つの助が重要だと思っている。自助については、各大学での教育が鍵になってくるので、育成という意味で今後も頑張ってもらいたい。互助については、周囲の意識も変わり始め理解が進んでいるものと考えられる。共助は、病院の制度整備も進んでいるので、今後ますます普及していくことを願うばかりであると、保坂日医女性医師支援センター副センター長から、日医の女性医師支援の取り組みが全国に広がっており、大変嬉しく思った。現在、女性医師支援で一番必要なのは、保育問題であると日々実感しており、保育問題解決のため国の予算も確保できるよう働きかけていきたいと総括された。
◇
当日参加された足立コーディネーターの感想記を以下に掲載する。
| 北海道医師会女性医師等支援相談窓口 コーディネーター 足立 柳理 |
 この度、2月27日に東京で開催されました日本医師会女性医師支援事業連絡協議会に初めて参加し、北海道医師会で行っております支援事業の報告をさせていただく機会を頂戴しました。
この度、2月27日に東京で開催されました日本医師会女性医師支援事業連絡協議会に初めて参加し、北海道医師会で行っております支援事業の報告をさせていただく機会を頂戴しました。当日は快晴の良い天候に恵まれ、日本医師会館大講堂で開催されました。
会は日本医師会笠井英夫常任理事の司会で始まり、冒頭に女性医師支援センター長の今村聡副会長から「女性医師支援事業の活性化のため、全国各地の特徴ある取組等の情報を共有することで、他の地域での事業展開に役立ててほしい」とのご挨拶がありました。
次いで横倉義武会長から「日本医師会女性医師バンク」は平成19年1月の開設以来現在まで400件を超す就業実績をあげていることを改めて評価し、向後女性医師の活躍は日本の医療の望ましい発展のためには必要不可欠なものであり、日医としてもその実現のために真摯に取り組みを進めていきたいというお考えが示されました。
その後議事に入り、はじめに福島靖正厚生労働省大臣官房審議官から「国における女性医師支援の取り組み」と題してのご講演がなされました。その中で「女性医師キャリア支援モデル普及推進事業」が開始され、今後に生かされることを期待しているとの説明がありました。
引き続き、全国6ブロックの中で特徴的、先進的な取り組みをしている地域からの報告が行われました。
北海道からは、現在全道的に取り組んでいる北海道医師会の相談窓口事業、育児支援、特に病後児支援、復職支援の3本柱が上手く機能していること、そして、実際に女性医師の声を活動に生かして進んでいること、また、長瀬北海道医師会長が製薬会社等で行っている各講演会における託児室の設置を北海道医薬品卸売事業協会へのお願いなどを通して各地域の勉強会に女性医師を参加させる動きを支援していることなどを発表致しました。
 その他、各ブロックで医科大学での取り組み、過疎化地域での取り組みなどの発表がなされましたが、皆さん女性医師が復職することの大変さ、子育てを行いながら医療活動継続の為の環境づくりに大変努力されていることが理解できました。しかし、個人個人の置かれた立場や境遇が異なるためその対応の仕方は千差万別で、ワークライフバランスや一人の患者にチーム体制で臨む診療体制の取り組み、ベテラン指導医紹介事業なども報告されました。それにもまして、地方においては、医師そのものの数が不足しているわけですから都会のようなわけにはいかない現実も直視できました。辺境の地で頑張っている女性医師にとって、男性医師でさえ少ない現実の中で如何に診療と子育てを充実させるかは永遠の課題であると思います。女性の医学部入学者が定員の30%を超える現在、この30%を上手く活用しなければ日本の医療は崩壊してしまう事は自明の理であります。
その他、各ブロックで医科大学での取り組み、過疎化地域での取り組みなどの発表がなされましたが、皆さん女性医師が復職することの大変さ、子育てを行いながら医療活動継続の為の環境づくりに大変努力されていることが理解できました。しかし、個人個人の置かれた立場や境遇が異なるためその対応の仕方は千差万別で、ワークライフバランスや一人の患者にチーム体制で臨む診療体制の取り組み、ベテラン指導医紹介事業なども報告されました。それにもまして、地方においては、医師そのものの数が不足しているわけですから都会のようなわけにはいかない現実も直視できました。辺境の地で頑張っている女性医師にとって、男性医師でさえ少ない現実の中で如何に診療と子育てを充実させるかは永遠の課題であると思います。女性の医学部入学者が定員の30%を超える現在、この30%を上手く活用しなければ日本の医療は崩壊してしまう事は自明の理であります。
医師となった女性が、そのモチベーションを落とすことなく先進医療に従事し、離職しないような環境づくりは医師会だけの対応で解決する問題ではなく、国と地方自治体とが一体となった対応して行かなければならない大きな問題であることを痛感しました。
現在の医療体制がすこしでもより良い方向に改善する事を願いつつ帰路につきました。
※お名前の旧字体は、新字体で表記しておりますのでご了承願います。