第18回男女共同参画フォーラム
令和6年4月27日(土)14:00
香川県・JRホテルクレメント高松
常任理事・医療関連事業部長 水谷 匡宏
第18回男女共同参画フォーラムが、去る4月27日(土)に香川県医師会の担当により高松市にて開催された。参加者は219名であった。
今年は「超高齢社会に向けての男女共同参画〜人生100年時代における多様な医師の働き方〜」をメインテーマに、日本医師会・松本会長、香川県医師会・久米川会長、香川県・池田知事の挨拶の後、基調講演が行われた。
◇
基調講演「女性医師を取り巻く諸問題」
前 香川大学 学長/香川大学特命教授/香川大学イノベーションデザイン研究所所長 筧 善行
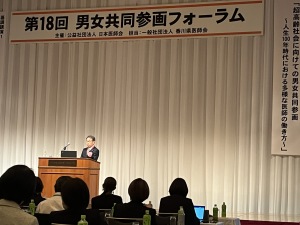 2018年夏に首都圏の私立医科大学において、女子の受験者を一律に減点したことが報道された。その後の国公私立大学81校を対象にした文部科学省の緊急調査では、入試で性別や浪人年数などにより合否に差異を設け、7割以上の大学で男子の合格率が高いことが判明した。この問題の背景には、我が国の医学界における女性医師差別が潜んでいると考えられる。日本の女性医師の割合はOECD加盟国中最下位である。
2018年夏に首都圏の私立医科大学において、女子の受験者を一律に減点したことが報道された。その後の国公私立大学81校を対象にした文部科学省の緊急調査では、入試で性別や浪人年数などにより合否に差異を設け、7割以上の大学で男子の合格率が高いことが判明した。この問題の背景には、我が国の医学界における女性医師差別が潜んでいると考えられる。日本の女性医師の割合はOECD加盟国中最下位である。 日本で西洋医学を初めて修得し実践したのは、ドイツ人医師シーボルトの娘、楠本イネである。初めて医師国家試験に合格した荻野吟子は自身の屈辱的な体験をばねにして女性のためということを志して産婦人科医となり、地域医療に貢献した。この話は一粒の麦という映画にもなっている。先駆者たちの奮闘により日本での女性医師数は7万人を超えている。
日本で女性医師数が少ない原因としては、離職率が高いことや女性医師の働く環境の整備不足が考えられる。医療分野における国際比較をみると、日本は他国に比べて1人あたりの医師の負担が過大となっている。
今回の医師の働き方改革を契機として、昼間のみ働くなどのママさん医師の働き方オプションを作り、女性医師を人的リソースとして生かす、男性医師も女性医師のモデルケースを通じてキャリアアップへの支援の仕方を理解する、などジェンダー平等を進めていきたい。
基調講演「フェムテックサービスを活用した、女性の働き方改革、妊娠期のQOL向上サポートの取り組み事例 安心・安全な出産を世界中のお母さんへ」
メロディ・インターナショナル株式会社CEO 尾形 優子
フェムテック(Femtech)は、FemaleとTechnologyをかけ合わせた造語で、女性が抱える健康課題をテクノロジーで解決する製品やサービスなどを指す。日本では増加する高齢出産、減少する産科病院により、出産がハイリスク化している。日本の母子死亡率は世界一低く優秀であるが、新興国や発展途上国では母子死亡率が非常に高くなっている。日本の母子死亡率が低下した要因として、1974年に世界初「胎児モニター」(分娩監視装置)がある。当社は2019年に、分娩監視装置を超小型化及びIoT化したiCTGを開発した。この装置は本体機能、センサー、スピーカーが一体化されたものであり、当該装置を2つお腹につけることでインターネットに繋がるところであれば、計測場所もデータを診る場所も選ばないという特徴がある。データはクラウドに保存されるため、医師は遠隔でモニタリングすることができる。
 医療機関や自治体での取り組みとしては、北海道大学病院で2020年3月に妊婦オンライン診療で活用されたほか、全国の一部医療機関や今回の能登半島地震でも活用されている。さらに、経済産業省のフェムテック等サポートサービス実証事業補助金を活用し、対象者を北海道余市町の妊婦、サービス提供者を小樽協会病院などとして実証事業を行った。12名の妊婦が在宅での妊婦健診を受診し、利用者からは切迫早産などの心配が減り、職場に行くかどうかの判断にも活用できると高評価を得た。
医療機関や自治体での取り組みとしては、北海道大学病院で2020年3月に妊婦オンライン診療で活用されたほか、全国の一部医療機関や今回の能登半島地震でも活用されている。さらに、経済産業省のフェムテック等サポートサービス実証事業補助金を活用し、対象者を北海道余市町の妊婦、サービス提供者を小樽協会病院などとして実証事業を行った。12名の妊婦が在宅での妊婦健診を受診し、利用者からは切迫早産などの心配が減り、職場に行くかどうかの判断にも活用できると高評価を得た。 また、海外での取り組みも進めており、タイやブータンなど海外16か国、128台を導入済みである。フェムテックデバイス(iCTG)でより安心・安全な出産ができるように協力したい。
◇
日本医師会男女共同参画委員会および日本医師会女性医師支援センター事業の活動について報告があった後、3人のシンポジストから話題提供があった。
(1)若手総合診療医が取り組む次世代の在宅医療
医療法人社団慈風会在宅診療敬二郎クリニック院長 西信 俊宏
在宅医療の患者は、循環器、糖尿病、悪性腫瘍など複数の疾患を抱えていることも多く、さらに、介護度が要介護3以上で外出が困難な方が約半分を占めている。在宅医療の課題としては、人材(マンパワー不足)、システム(急変時の後方支援、患者家族の介護の負担軽減)、教育(看取りなどの知識)の3つが挙げられる。
当院の課題解決への取り組みとしては、まず法人の理念を明確化・言語化して、チーム制で診ることとし、訪問看護師など多職種で協力して対応している。また、DXとして、クラウドカルテの導入、多職種連携に係るITツールなどを活用して、女性スタッフなども働きやすい環境を整えるとともに、一部をアウトソーシングするなど効率化を進めている。教育も大事に考えており、複数の専門識者が共に学ぶような多職種連携の教育を進め、若い医師にも在宅医療に興味を持ってもらうようにしていきたい。
(2)大学病院勤務医の役割と課題
香川大学医学部総合診療学講座 講師 石川かおり
香川県の人口は約90万人で高齢化が進んでおり、全国で最も面積小さい県である。大学の役割としては、教育、医療、研究の3つある。大学で働く一個人としては、教師、医師、妻(母)としての立場、研究者など、多種多様な役割を担っている。大学病院で働く強みとしては、先進医療ができる、研究のしやすさ、学内外の人脈の構築ができるなどである。一方、弱みとしては、低賃金、業務が多忙、ポストが少なくベテラン医師が少ない。全国の種別ごとの医師数をみると、一般病院は平均47.6歳、大学病院は平均39.6歳となっており、大学病院は若手医師に支えられていることがわかる。
結婚や出産などライフイベントに応じて、個々の仕事へのモチベーションに変化がある。40代や50代にはキャリア転換期、60代以降はモチベーションや身体的機能の維持などの変化があり、大学病院としてはテーラーメイドな対応や支援が求められる。当大学としても、学びたいという方に対してAIやVRの活用など、若い先生方にとって魅力的に映る場所にしたい。
大内胃腸科眼科医院 副院長 大内 通江
私は岡山大学医学部卒業後、同大学眼科学教室に入局し、結婚を経て無給医時代に2人の娘を出産し、眼科医院を開業するに至った。その後、還暦を迎え、後輩の育成に目を向け、医師会活動を行うことにシフトした。医師会活動では、学校医活動や慢性疾患の療養指導・相談、視覚障害者支援、アイフレイル対策活動などを行っている。
私が「継続」していることは、常に学ぶこと、健康を大事にすること、人的ネットワークを作ること、変化に向き合うこと、経済的基盤を持つことである。反省を込めて気づいた「努力目標」としては、高い志と強い心構えを持つこと、困難にぶつかったときに社会や性差のせいにして逃れないこと、社会的・個人的に支援を受けた時は義務と権利のバランスを持つことなどである。患者さんは明るく快適な毎日を過ごしたくて病院に足を運ぶので、医者もいつまでも元気な姿で、患者さんと共に考える医療で応えたいと考えている。
◇
続いて、総合討論ではシンポジストと参加者の間で活発な意見交換があった。
その後、次期担当県の福島県医師会・佐藤会長より、令和7年5月17日(土)に郡山市にて開催予定であると挨拶があり、盛会裡に終了した。

