健康レシピとエクササイズ
recipe&exercise
北海道国民健康保険団体連合会 機関誌「北海道の国保」に
掲載の中から健康レシピとエクササイズをご紹介いたします。
健康レシピ
(管理栄養士監修)
北の恵みふるさと健康料理2025年10月号
恵庭市の特産 えびすかぼちゃ

エクササイズ
自宅でできるエクササイズをご紹介します。(一般社団法人 地域ウェルネス・ネットより)

ウェルネス・ネット代表
福岡永告子 先生
Youtube
転倒予防体操 ③(2025年8月号) ~長く自分の足で歩くために~
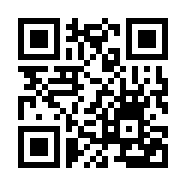
- 「歩く」は健康のバロメーター
-
「歩く」という行為は、ふだん私たちが最も頻繁に行っている行為です。 そして、この歩行の維持は「健康長寿」を維持する上でとても重要な役割を果たすことが実証されています。介護予防教室の参加者からも「いつまでも自分の足で歩きたい」「トイレに自分で行き排泄する力を失いたくない」と切実な声も聞かれます。
- 高齢者が「歩けなくなる」原因
-
高齢者が歩けなくなると、希望に沿った生活が遠ざかり、生活の質(QOL:Quality Of Life)も低下します。買い物や、通院ができなくなり、自宅に閉じこもりがちになって、心の健康にも影響を及ぼします。
高齢者が歩けなくなる原因はさまざまありますが「筋力の低下」や「慢性疾患の既往」「骨や関節の疾患」などが挙げられています。
①運動不足
「使わない筋肉はなくなる」といわれています。特に高齢になると、意識して動かないと、どんどん筋肉は減ってしまい、足の老化が加速します。
②関節の痛み
歩くときに必要な関節である膝や股関節に痛みがあると、自然と体を動かさなくなります。そうすると、筋肉を使わなくなって、どんどん筋力が落ちてしまうのです。「痛いから動かない → 筋肉が弱る → もっと動けなくなる」という悪循環に陥ります。
③認知症の影響
認知症の中で最も多い「アルツハイマー型認知症」では歩幅が狭くなり、すり足でゆっくり歩くという特徴があります。さらに背中が丸まって前かがみの姿勢になるため、バランスを崩しやすくなり、転倒のリスクが高まります。
④入院による体力の低下
入院中は安静にする必要があるため、活動量が減って体力の低下を招きます。年齢を問わず、1週間〜2週間程度の入院でも想像以上に筋力は落ちるといわれています。
⑤低栄養によるエネルギーの低下
体を動かすのに必要なエネルギーや、筋肉や骨などを作るタンパク質が足りない状態になり、筋肉量も落ちて活動量が減ってしまう。
- 歩くために必要な筋力
-
「歩く」ためには地球の重力に逆らって体を持ち上げ、背骨を伸ばして支え続けることが必要です。「重心」といわれるものを移動させるために、足や手(前足)の上に背骨をしっかりと安定させてのせておくことが必要になってきます。
今回は、鍼灸師、柔道整復師、介護福祉士の企画編集で、
・脚 (踏む力、蹴る力)
・背中(腕を引く力、背中を支える力)
・お腹(足を引き上げる力、お腹を支える力)のプログラムをご紹介します。
動画では自分の体のチェックもできるプログラムから始まります。
ぜひ、動画も活用していただきたいと思います。
転倒を防いで、いつまでも自分の足で歩いていきたいですね!
秋こそウォーキングの季節(2025年9月号) ウォーキングのポイント

- 秋のウォーキングの健康効果
-
今年の夏は本当に暑い日が続きました。
夏バテで低下した体力の回復のためにも、残暑もやわらぐ9月ごろからウォーキングを始めてみませんか。涼しくて過ごしやすい季節である秋こそウォーキングがおすすめです。
また、「食欲の秋」といって秋は食欲が増す季節ですが、ウォーキングをすることで体重管理がしやすくなります。特に、秋に運動を始めると基礎代謝が上がり、ダイエット効果も期待できるため冬太りの予防にもなります。
秋の美しい風景を楽しみながら、外の空気を吸ったり季節のうつろいを感じたりして心のリフレッシュを図ることは自律神経の働きを正常に戻す効果があります。
私たちの体は、見えないところで常に自律神経が活動を調整しています。この微妙なバランスが崩れると、体調不良やメンタルの不調を引き起こすことがあります。だからこそ、自律神経を整えることは、健康で充実した毎日を送るために非常に重要なことです。
- ウォーキング時の靴と靴下
-
・靴
ウォーキングをするときに履くシューズは、普段履くものではなくウォーキング用につくられたものをおすすめします。できれば試し履きをしてフィット感を確認し、自分の足に合うかチェックしてください。クッション性に優れたシューズを選ぶことで、足への負担が軽減され、歩きやすさをサポートする効果も期待できるので、靴を選ぶ時の参考にしてください。
-
・靴下
歩いているときに靴の中でソックスが滑ると、足に負担がかかる場合もあるため、ウォーキング時のソックスは滑り止め加工が施されたものをできれば選びましょう。
また、足のサイズに合っているものを選ぶこともポイントです。サイズの合わない靴下を履いていると歩いているうちにずれてきて、不快に感じることもあるため注意しましょう。
また、長時間歩くと汗をかいたり蒸れたりして臭いがこもることがあるため、抗菌防臭機能が備わったものがあればさらに良いと思います。
- ウォーキング時の注意点とコツ
-
・水分、エネルギー補給も忘れずに、こまめに摂りましょう!
涼しくなった秋でも歩くと汗をかくので脱水症状に注意しましょう。また、食前のウォーキングがダイエットに効果的といわれていますが、空腹時の運動は、血糖値の急降下や運動能力の低下につながることもあります。
早朝の起き抜けは特に、脱水になりやすいのでスポーツ飲料などの水分摂取のほか、バナナやヨーグルトなどを軽く口にしておくと安心です。 -
・距離よりも時間で歩こう!
運動をしていない人がいきなり長距離を歩こうとすると、膝などを痛めやすくなります。様子を見ながら徐々に歩く時間を増やしていくようにしましょう。時間を決めて歩くことで計画も立てやすくなります。私も1日のスケジュールに合わせて時間を決めて歩いています。歩数計があれば自分のペースと運動量が確認できるのでモチベーションに。
-
・ウォーキング前後に準備体操を!
ウォーキング前後には、関節や筋肉をほぐすストレッチを数分行うのがおすすめです。ウォーキングが運動のメインなので、あまり時間を要さない簡単で必要なストレッチをご紹介します。
時間が取れれば、生活圏内から離れた、自然の中でのウォーキングで、秋を彩る景色も楽しみましょう。
3つの基本運動 有酸素運動・筋力トレーニング・ストレッチ(2025年10月号) 自重トレーニング


- 有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせて効果up
-
運動には様々な種類がありますが、その中でも健康増進に必要な基本運動は「有酸素運動」「筋力トレーニング」「ストレッチ」の3つになります。
有酸素運動とは酸素を使いながら軽度から中程度の負荷を継続的にかける運動のことで、ウォーキングやジョギング、サイクリングやエアロビクス、ダンスなど手軽にできる簡単な運動が多く、初心者でも取り入れやすいのが特徴です。
筋力トレーニング(筋トレ)は、筋力に負荷をかける運動のことで、道具を使って負荷をかける「ウエイトトレーニング」と、自分の体重を使って負荷をかける「自重トレーニング」に分類されます。
有酸素運動は脂肪燃焼効果も高いので「痩せたいから有酸素運動をがんばりたい!」という方は多いと思いますが、有酸素運動を長く行うためには筋力も必要です。ダイエット目的の場合は筋トレを先に行い、有酸素運動はその後に行うと効率よく脂肪を燃やすことができます。
- 自重トレーニングのメリット
-
・器具が不要でいつでもできる
運動には様々な種類がありますが、その中でも健康増進に必要な基本運動は「有酸素運動」「筋力トレーニング」「ストレッチ」の3つになります。
有酸素運動とは酸素を使いながら軽度から中程度の負荷を継続的にかける運動のことで、ウォーキングやジョギング、サイクリングやエアロビクス、ダンスなど手軽にできる簡単な運動が多く、初心者でも取り入れやすいのが特徴です。
筋力トレーニング(筋トレ)は、筋力に負荷をかける運動のことで、道具を使って負荷をかける「ウエイトトレーニング」と、自分の体重を使って負荷をかける「自重トレーニング」に分類されます。
有酸素運動は脂肪燃焼効果も高いので「痩せたいから有酸素運動をがんばりたい!」という方は多いと思いますが、有酸素運動を長く行うためには筋力も必要です。ダイエット目的の場合は筋トレを先に行い、有酸素運動はその後に行うと効率よく脂肪を燃やすことができます。
- 自重トレーニングをさらに効果アップ
-
・回数を多く行う 目標:8~10回×2セット
・インターバルは短く
セット間のインターバルが長いと筋肉が休みきってしまい、筋肥大の効果が薄くなってしまうので、インターバルは30秒以内にしましょう。
-
・ゆっくりとした動作で行う
ゆっくりとした動作で筋肉をしっかり収縮、緊張させましょう。呼吸も忘れずに。
-
・週3回の頻度で取り組む
負荷が弱い自重トレーニングはその分回復も早いので、定期的にトレーニングをして、筋肉が休養しすぎないように心がけましょう。最低でも週に3回は行いましょう。
-
・筋肉痛の時は休む
筋肉痛のときは休みましょう。筋肉痛は筋肉が炎症を起こしている状態です。この休息時間がより強い筋肉をつくることにつながります。
-
・有酸素運動とストレッチを組み合わせましょう
時間がある時には、ウォーキング、ストレッチ(動画もあります)を組み合わせてオリジナル運動プログラムを作成、実践してみてください。
